|
|||||||||||||
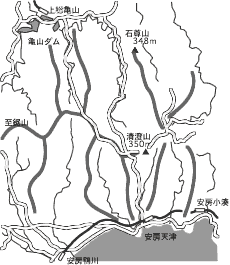 昨年11月末、房総半島南部(千葉県)の低山に日帰りハイキングに出かけた55歳から83歳までの30人が、道に迷って一晩ビバークする事故がありました。ビバーク翌朝には全員無事に下山したのですが、地元では前夜からの170人態勢に加え、翌早朝からはヘリコプター3機、300人態勢で捜索する騒ぎになりました。この山行は、君津市の養老渓谷付近から石尊山、麻綿原高原を経て天津小湊町の清澄山へ向うものでした。「千葉こまくさハイキングクラブ」では、かつて会員が同じようにこの山域で道に迷った様子を報告した文章を、事故直後に発行された会報「こまくさ便り」12月号に再録して、改めて注意をよびかけています。 昨年11月末、房総半島南部(千葉県)の低山に日帰りハイキングに出かけた55歳から83歳までの30人が、道に迷って一晩ビバークする事故がありました。ビバーク翌朝には全員無事に下山したのですが、地元では前夜からの170人態勢に加え、翌早朝からはヘリコプター3機、300人態勢で捜索する騒ぎになりました。この山行は、君津市の養老渓谷付近から石尊山、麻綿原高原を経て天津小湊町の清澄山へ向うものでした。「千葉こまくさハイキングクラブ」では、かつて会員が同じようにこの山域で道に迷った様子を報告した文章を、事故直後に発行された会報「こまくさ便り」12月号に再録して、改めて注意をよびかけています。注意をよびかけたのは同クラブ会長の古瀬健さん(千葉県連盟会長)。この山域が300〜400メートルの低山とは言うものの、実際はどのようなところなのか、そして「道迷いへと追い込まれていく様子」が綴られた再録報告――それぞれを転載させていただきました。 なお、千葉県は今回の事故を受けて、県庁各部局と関係市町村、県山岳連盟、労山千葉県連盟を集めて道標整備の検討会議を開いています。その席上、今回の事故の「原因」について、消防地震防災課から(1)ガイド役3人が同行していたが下見がなかった(2)計画がずさんだった(清澄山到着見込が17時だった/平均年齢70歳を考えると無理な行程だった)(3)コース上に案内標識がなかった――などが指摘されました。また、このパーティーのリーダーの方は新聞紙上などで、無事下山できたのは、メンバーがビバークに耐えうる装備・非常食などを携行しており、「ビバークを決断できたのも自分勝手な行動をとる人がいなかったから」だと語っていました。
県の道標整備の検討会議は、引き続き開催されることになっており、千葉県連盟では、整備のあり方についての会員の意見や、会員がどのように千葉の山を登っているのかの実態を集約して臨むことにしています。
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
この山行は、当会と同様のランク制のもとに「こまくさコース(Bランク)」並の山行としておこなわれたという(千葉こまくさHCは4ランク制で運営されている。Bは容易なほうから2番目出、4〜5時間行程、多少の岩場、鎖場もありあえる/編集部)。体力的に、また登山技術的には問題のないコース選定であったと思う。また、参加者の装備、行動、判断なども、しっかりしていたと思う。では、なぜこのような事態に陥ったのであろうか。この原因にこそ、千葉の山の特徴があると思うのである。 第1には、ハイキングコースとしての整備がされていない。1973年の千葉国体のときに多くのコースが拓かれたが、ほとんどのコースがそれ以後放置されてきた。例えば、メインコースとしての房総脊梁・鋸山から清澄山のうち、道とよべるのは保田から日本寺の遊歩道までで、鋸山の三角点までも一般道ではない(ここで言う房総脊梁とは、半島南部を東西に横断している丘陵地。清澄山は太平洋側、鋸山は浦賀水道側/編集部)。ましてその先は、道なき道を求めるがごとくである。小保田からあがった脊梁上の嵯峨山に至るコースも、山頂から先はヤブ漕ぎである。林道部分を除くと、ほとんどはテープを頼りに地図とのにらめっこが続く。こうしたことは、この3年、千葉県連盟の仲間で踏査してみて明らかになっている。 第2に、高度差のない尾根が複雑に入り組んでおり、踏跡や獣道が多く、コースの判断が難しい。第3に、沢の側面はほとんどが10・以上、ときには100メートル近い絶壁で、行く手を遮られる。第4に、このような事情が伝わりにくいために、山が低く距離が短い手頃なコースと誤解されやすい。
千葉在住のわれわれですら、先に「千葉ぶらぶら20選」なるコースガイドを書いていながら、ポピュラーなコースしか扱っていないので、千葉の山のこうした特徴を本当に紹介するものにはなっていなかった。筆者自身も、理解できたのは最近のことである。この房総脊梁では道迷いによる死亡事故が何件か起きている。このパーティーも下見は必要であったと言えよう。当会の先輩、中水流探心さん(故人)が、まさにこの石尊山界隈での道迷いの顛末を克明に記した手記を古い「こまくさ便り」に掲載されていた。参考にしていただきたい。
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
私は暮の22日、足慣らしのつもりで家内と2人、清澄寺の奥の石尊山へ登ってみた。山麓の清澄温泉に車を預けて「標高325メートルの丘でも散歩するか」などと軽口を叩きながら1時間ほどして山頂に着いてみると、無線塔の工事でブルが山肌を掻き均しています。なんとも風情がなく、四方八方どちらを眺めても房総特有の丘のように低い名もなき山々がさざ波のように連なり、背伸びをしても跳び上がっても太平洋の水平線は発見できす、いささか期待外れ。 少々物足りない感じで、もうひと尾根越えてみるかと1時間ほど歩いてところで、「待て暫し、きょうは冬至だ、暮れるが早いぞ」――帰りがけに山草でも少々仕入れたいし、露天風呂にも浸かっていきたい。回れ右だ! 踵を返して下山道をしばらく下ると、何だか様子が異なる。靴跡を探してみても一向にない。あるのは鹿の足跡ばかり。家内が「こんな急坂を登った覚えがない」と言い出した。 どうやら、ひと谷左にそれたらしい。道標は皆無である。「エーイ、面倒だ。下っているかぎり県道のどこかに顔を出すさ」と甘く考えて、強引に下ってみるが、山はますます深まるばかり。道はかすかな踏跡程度になる。いささか不安を感じて逆戻りとなる。「山の鉄則を無視したバチだ」とブスブスこぼすことしきり。分かれ道まで戻って一息入れ、右手に道をとり、今度は間違いないと歩みを速める。 軟岩がところどころ顔を出していて滑る。足をとられる。枯れ枝をつかんだかなと思った途端にポキンと折れて、横面をパチンと叩かれた。瞬間、目の前がかすんで霧の中にいる。――「しまった、メガネが吹っ飛んだ」「さあ、困ったぞ。踏みつぶしたら一巻の終りだ」。その場でそっと四つん這いになって、近眼の眼を地面にすりつけんばかりにして探しはじめたが、夕闇はもうそこまで迫ってきている。深く積もった落葉のヤブの中から、色のはっきりしないメガネを探しだすのは至難の技である。8割方諦めかけていると、崖の下の方から「あった!」という家内のすっとんきょうな声。そんな下の方まで飛ばされていたのか、やれやれ助かった。思わず「ありがとさんヨ」と声が出た。 態勢を立て直し、なおも下る。あれれ……。またしても道が消えかけ、やがて行き止まり。前を覗けば断崖絶壁の渓谷ではないか。まるでキツネにでもつままれたような感じ。唯々呆然。じっと耳を澄ますと、対岸の方にかすかに車の走る音がするようだが、何分垂直に近い15メートルの軟岩の絶壁だ。ロープでもないかぎり、渡るのは到底不可能である。無念詮方なし。またしても逆戻り。 分かれ道まで戻ったときには、山はもうとっぷり暮れて視界はまったくない。まるで下山道を神隠しにでもあったようだ。「俺たち何も悪いことをしていないのになんでヤア」と闇に向って叫んでみても、山は寂として声なし。木霊すら返らず。「清澄山系は道標がなく、尾根が複雑で、過去に幾度か遭難まがいの事故があった」というような記事を何かの本で読んだような記憶が、チラッと頭をかすめた。「ここでジタバタするなよ」「先ず落ち着け」と体に言い聞かせ、足を休めてジックリと作戦を練るべしと、落葉の上に寝転がる。散歩気分できているから、ザックの中にはランプも地図も防寒着もない。この場の野宿では到底夜の寒気に耐えられそうにない。家内の声にも、すっかり元気がなくなってきた。 さあいかにすべきか……。しばらく思案を巡らせた挙げ句、ふと空を仰げばなんと5日くらいの月が顔を出している。ほんのり山道が浮かび上がって見えるではないか。「しめたぞ、これで行動できるぞ」。緊張感がほぐれると、脳も回転しはじめる――「そうだ! 無線塔の工事現場に基礎を埋める大きな穴があった」――あの中で枯れ枝を燃やして夜を明かすべしと心を決め、月明かりを頼りに石尊山頂に向って逆行をはじめる。五体は疲労の極に達しているが、気持ちがリラックスすると、さらに推理も展開しはじめる。ブルがあり、資材が積んであるということは、それを運搬する工事用道路が必ずあるはずだ。それを辿れば人家が発見できるはずだ。家内が小躍りした。五体に元気がみなぎり、急に足が軽くなってきた。現場に辿り着いて月明かりで探してみると、案の定、4メートル幅の立派な道が麓へと向っているではないか。「やった、やった」、思わず心の中で叫んだ。3キロほど下ると、果たして暖かい色をした人家の灯が小さく見えてきた。 ――事情を話して車を出していただくべくお願いしたが、あいにく老夫婦の2人暮らしで望みには応えられないが、温泉宿まで20分くらいで歩けるからお茶でも飲んでゆっくり休んでいらっしゃいと、詳しい地図を書いてくれる。「夜道に日暮れなしや」。もう慌てることもなかろう。疲れ果てた五臓六腑に温かい一杯のお茶がしみわたる。ああ甘露なるかな……。心ばかりの謝礼を膳の端に置き、地図を後生大事に握りしめて、しんしんと寒気身に沁む夜道を急ぐ。県道に辿り着いた頃振り返って見ると、ご老人がスクーターで追いかけてきて「ランプを持っていらっしゃい」と言う。人情に胸の熱くなるのを覚えながら、あと1キロちょっとの道に最後の力を振り絞る。ガクガクの膝頭を引きずりながら車に辿り着く。車のドアに手をかけながら、家内がすばらしい笑顔でにっこりほほえんだ。
|
|||||||||||||